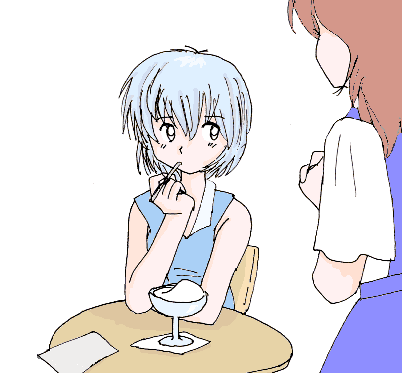「Big or Small?」
samy@ka2.so-net.or.jp
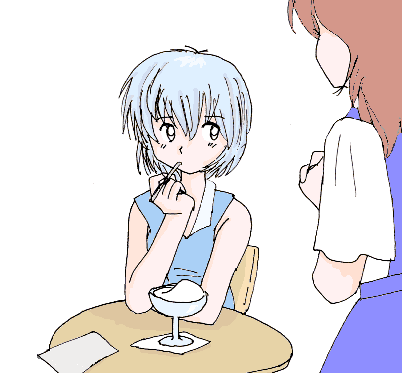
「綾波さん、ですよね?」
その日、あたしは学校近くのファミレスでアイスクリームをちびちびと
食べる至極の時間を味わっていると、知らない女の子が話しかけて来た。
あたしが誰だろうと考えあぐねていると、その子の後ろからアスカが
現れた。
「やっぱりここにいたのね、レイ」
「アスカ? どうしてここに?」
「あんたを探してたのよ」
どうしてここと分かったんだろうか。
「食い意地の張ったあんたのことだから、ファミレスにでも居るかと思えば
案の定ね」
「それは偏見よ。‥‥まあ、確かにそうだったのかもしれないけど」
「そんなことはどうでもいいわ。彼女はうちの陸上部員なんだけど‥」
「はじめまして、綾波さん」
その子はぺこりと礼をした。あたしはスプーンを持ったまま軽く会釈する。
「綾波さん、陸上部に入りませんか?」
「へ?」
「アスカさんにうってつけの方がいるって紹介してもらったんです」
「えーと、あたし、走るのが得意ってわけじゃあないんだけど」
と言いつつ、毎日遅刻ぎりぎりで走っているから、自信が無いわけじゃない。
でもそういうことではないようだ。
「レイ、あんた結構、足早いじゃない」
アスカが横から口を挟む。
「そう?」
「そうよ。それに体型が走るのに適してるのよ」
「‥‥‥‥‥どういう意味よ」
アスカは皮肉っぽい笑みを浮かべると、
「空気抵抗が少ないってことよ」
「ちょっと! それってあたしの胸が小さいってこと!?」
「まあ、そうとも言うわね」
ガタン!
あたしは思わず立ち上がった。
「ちょっと! だったらアスカだってそうでしょ?」
「わたしはレイと違ってプロポーションが良すぎるのよ!」
とポーズを取る。
「たいして変わらないわよ!」
とあたし。
それまで忘れていた、陸上部の彼女がおずおずと話に割ってきた。
「あの、綾波さん? それで入っていただけます?」
「‥‥‥遠慮するわ」
あたしは力無く言った。
次の日、教室に行くと相田君の席へ向かった。
「相田君、ちょっといいかな」
「ああ、綾波か。なんか用なのか?」
「例のアルバム、見せてくれない?」
そう、相田君があたしたち女生徒の生写真を男子に売っているというのは、
女子の間でも有名なのだ。
「へ、変な写真は無いぞ!」
「わかってるわよ」
「‥もしかしてそっちの方面の趣味なのか?」
「馬鹿なこと言わないでよ!」
相田君は机の中からアルバム帳を取りだした。あたしはそれを受けとり、
自分の席へ戻ると早速ページをめくる。
ふむふむ‥‥。なるほど、確かにかわいい子ばかりね。
隠し撮りのようだが、別にいかがわしい写真はなかった。
だが、あたしはそんなことをチェックしてるわけではない。
うーむ。‥‥みんな結構、胸、あるのね。
思わず自分の胸元を見てしまう。
「レイ、なに自分の胸と比べてるのよ」
「ア、アスカ、いきなり後ろに回らないでよ!」
あたしは慌ててアルバムを閉じる。
「どう、あたしのスタイルの良さが分かったでしょ」
「ど、どうだか。アスカだってあたしとそんなに変わらないわよ」
「‥なるほど、もっと胸が大きくなりたいってわけか」
と相田君。気付けば、碇君と鈴原君もやって来ている。
う‥、碇君に聞かれたかしら。
「なんや、そんなことかいな」
悪かったわね。
「あんたら、3バカはあっち行ってなさいよ」
アスカが追い払おうとする。
「まあ惣流、俺たちにいい案があるんだ」
「なんのことよ」
「胸を大きくする方法だよ」
相田君の言葉にあたしは思わず身を乗り出す。
「なんでも男に揉んでもらうといいって話だぜ」
「ななな、何言ってんのよ!」
アスカはちょっとひるむ。
「そや、どや、わいらが協力してやろうか」
「ああ、綾波と惣流のためだ。僕らも協力は惜しま‥‥」
ドカカッ!
「ったく、気色悪い!」
アスカの蹴りが二人を壁まで飛ばし、壁の一部と化した。あ、倒れた。
全くしょーもない。
でも、もしかしたら本当だったりして‥‥ね。
その時、碇君は二人のノリについていけず立ち尽くしていた。
「ねえ、碇君、‥‥」
わたしは振り向いて碇君をじぃーと、見つめる。
碇君とあたしの視線が合ったまま固まってしまう。
「‥あ、綾波?」
碇君が声を絞りだし、同時にのどがゴクリとなった。
「‥‥‥‥‥」
「‥‥‥‥‥」
「こらレイ! その乞うような目つきは何なのよ!」
「あははは、冗談だってば!」
あたしは手をパタパタと振る。
「あんたもよ、シンジ!」
「わ、わかってるよ」
碇君は苦笑いしている。
んふふふ、碇君、残念でした。
‥‥‥うーん、私もちょっと残念だったかもしんない。
「でも、胸が小さい方がいいって奴も多いんだぜ」
いつの間にか相田君が復活してやってきた。
「実際、綾波の写真だって、結構人気あるわけだし」
「そこであたしを出さないよーに」
相田君を睨みつける。
「い、いや別にそういうわけじゃ‥」
「ふーん、レイが代表的存在なの。じゃ、まさにあたしの対極にいるわけね。
ほーほっほっほっほっほ‥‥」
‥‥‥だれだ、おまえは。
「とにかく! あたしのこと胸が小さいとかいうの、やめてよね」
「まあまあ、写真で見る限り、惣流も綾波も似たり寄ったりだからさ」
「そやな」
相田君の横で、うんうんとうなづく鈴原君。
「いい度胸じゃない、相田に鈴原! 何を根拠にそんなことを言うのよ」
「根拠って?」
「ちゃんと数値で把握してるんならともかく、勝手な想像でもの言わないでよね!」
「そりゃ、そこまで把握してるわけじゃないけどさ」
「あったり前でしょ。バカシンジ以外にわかってたまるもんですか」
「な、なんだよアスカ」
突然振られて碇君が慌てる。
「アスカ、どういうことよ」
あたしは努めて冷静に問いかける。
アスカはあたしの問いには答えず、さらに碇君に向かって、
「シンジ、覚えてるわよね。なんたって、一緒にお風呂に入った仲なんだから」
!!
「責任とってくれるわよね、シンジ!」
「ちちちちちょっと待ってよ。それって幼稚園の頃じゃないか」
「そうよ、それがどうしたのよ」
「そんな子供の時の話をされても困るよ」
なーんだ、幼稚園の話か。
「だいたい、アスカの胸だってぺったんこだったじゃないか」
「失礼ね! 幼稚園児なんだから当然でしょ」
「だから、幼稚園の頃の話なんだから‥」
「バカね。論理的に類推すれば今の私の胸ぐらい想像出来るでしょ!」
「そんな無茶な‥」
そこに相田君が口を挟んできた。
「俺たちに想像させるととんでもないことになるぞ」
「そやな。この女の胸は多分‥」
「むむむ‥」
「むむむむ‥」
相田君と鈴原君は突然、目を閉じて瞑想を始める。
「見えた!」
「むぅ、全体はこぶりだが、にゅう‥」
「あほかーーっ」
アスカに張り倒されて、再び二人は壁へ貼りついた。そして、パタリと倒れる。
「あたしはシンジに言ったのよ! 誰があんたらに想像しろって言ったのよ!」
怒りのためか羞恥のためか赤い顔をしたアスカがピクリともしない二人に
言い放つ。
あたしは碇君をそっと手招きした。
それに気付いた碇君があたしところまでやって来る。
「なに、綾波」
「碇君は、‥‥その‥胸の大きい女の子と小さい子とどっちが好きなの?」
「へ?」
「‥‥碇君の好みを訊いてるの」
「‥‥‥‥」
「‥‥‥‥」
しばらく、沈黙が訪れる。
「僕はそういうのはどちらでもいいと思うけど‥」
「なーに言ってんのよ、男なら必ずどちらかに入るはずなのよ」
突然アスカが入り込んできた。
アスカは腰に手をあて、
「で、普通の男なら胸は大きい方がいいわよね〜、シンジ!」
「だから、僕は‥」
その時、チャイムが鳴り、同時に先生が教室へ入ってきた。
碇君たちも素早く自分の席へ戻っていった。
あたしも椅子を戻すと、教科書を開いた。
あーあ、なんだか中途半端になっちゃったな。
授業中、あたしは小さな紙に放課後に残ってほしいと書くと、折り畳んで
碇君にぶつけた。
碇君は紙を広げて読むと、わかったと目で合図をした。
そして、放課後。
あたしと碇君はなんとなく人気の無いところを探して、校舎の裏の方へ来た。
「ね、さっきのあたしの質問なんだけど‥」
あたしは期待で顔を真っ赤になっていたと思う。
「うん‥‥あの、綾波‥」
碇君も真っ赤になって声を絞り出している。
「その、綾波が小さい方だっていうなら、‥」
「‥‥」
「僕は胸が小さい子の方が好きなんだと思う‥」
「ほんと?」
「うん」
碇君‥。
お互いに見つめあったまま、しばらく無言が続いた。
‥‥‥。
‥‥‥。
これはチャンスかも。
あたしはそっと目を閉じて、‥‥
「あら、シンジくんに綾波さんじゃない」
ミサト先生がやってきた。
「シンちゃん、綾波さんと何やってるのぉ、うりうり」
と碇君を人差指でこづく。
「ミ、ミサト先生、やめてくださいよ」
「用も無いのに学校に残ってちゃだめよん」
ミサト先生は、いつもにも増して、胸のあたりのカットの大きい服を
着ていた。とどのつまり、胸の谷間を強調した服だ。
今までのこともあり、あたしはなんだかミサト先生の胸をつい、見入って
しまった。
うーん、あたしだって大人になればあれくらい‥‥。
でもあのお母さんの娘だもんなあ‥‥‥。
‥‥‥‥。
ふと気付くと、碇君も同じようにミサト先生の胸に目が釘付けになっている。
‥こら。
「じゃあ、気をつけて帰りなさい」
「はい、さようなら」
ミサト先生は駐車場の方へ歩き去った。
あたしは回り込んで、碇君の顔をのぞき込む。
「い・か・り・く〜ん、どこを見てたのかな」
あたしは、じと目で碇君を見つめる。
「え、あ、いや別に‥」
「どういうことなのかな」
逃げようとする碇君の腕を掴み、腕を組んだ。
「あ、綾波」
「だめよ、しっかり白状してもらうんだから」
しっかりと腕を組んだまま、あたしと碇君は学校から帰るのだった。
END